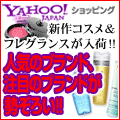2024年3月22日 更新
こんにちは ご訪問ありがとうございます。
ベランダで野菜や草花を育てる時の病害虫対策に使う薬剤の選び方、予防剤と治療剤について調べて解った事をまとめてみました。
病気や害虫から守るために使用する薬剤選びの参考になればと思います。
目次
予防剤と治療剤の違い
育てている野菜に何らかの症状が出ている場合に選ぶ薬剤と、症状が出る前に散布しておくべき薬剤とでは効き方や使い方も違って来ます。
例えば殺菌剤で言えば、病原菌が作物に入り込む前に防ぐのが予防剤で、作物の体内に侵入した病原菌を駆除するのが治療剤となります。
治療剤
既に病気が発生している作物に予防剤を使っても効果は期待出来ず、その場合は治療剤を使います。
治療剤の防除効果は高いとされていますが、その範囲はあまり広くありません。
たとえばうどん粉病やさび病だけに効く等、特定の病気に対して特異的な効果を示す薬剤が多いからです。
また、治療剤には耐性菌発生のリスクが高く、最初は効果があっても続けて使用すると効かなくなってしまう場合があります。
つまり治療剤の多くは特定の病気が出ている場合は効果が期待出来ますが、定期的な散布には不向きであると言えます。
耐性になりにくい予防剤
その点予防薬は定期的な散布を行うことで、病原菌が植物体内に入り込む前に防除することが可能です。
発病初期に散布して病原菌に直接散布すれば目に見えた効果を発揮することが出来ます。
スポンサーリンク
病原菌と病気発生までの過程
3種類の病原菌・カビ・細菌・ウイルス
薬剤には、予防剤と治療剤があることはお判りいただけたと思いますが、病気そのものについてもう少し詳しくみて行きたいと思います。
病原菌には、カビ(糸状菌)と細菌、ウイルスの3種類が存在します。
このうち80%弱はカビによって発病し、残りは細菌やウイルスによって発病します。
カビにより病気が発生するまで!
それでは、病気を発病させるリスクが最も高いカビの胞子が葉っぱに付着した後でどのような段階を経て病気を発病させるのかを簡単な図で説明致します。

①植物の表面についたカビの胞子が発芽するとそこから落ちないように付着器を作ります。
※植物に感染するために病原性カビの胞子は、植物の種のように発芽し、続いて『付着器』と呼ばれるドーム状の特殊な細胞を植物表面に形成します。
②菌糸を伸ばし細胞内に侵入。
酵素を出して葉の表面にあるワックス層を溶かしながら植物体内に菌糸を伸ばし細胞内に吸器を作ります。
③細胞から栄養をとり、分生胞子を作ります。
吸器で植物から栄養分を吸収 しながら繁殖し、再び 胞子を拡散、これを繰り返して増殖していきます。
①の段階では予防剤を使います。胞子の発芽を抑制したり菌糸の侵入を阻止します。
②・③の段階で治療剤を使います。 作物体内に成分が浸透、侵入した菌糸や吸器に作用して死滅させたり分生胞子の形成を阻害します。
うどん粉病の例
土や落ち葉の中に隠れていた(糸状菌)が風によって飛ばされ植物に付いて広がって行きます。
うどん粉病の場合絶対寄生菌で宿主植物の表面に吸器と呼ばれる器管を挿入して栄養を摂取して繁殖します。
※絶対寄生菌とは生きた宿主から離れた状態では増殖出来ない微生物のこと
葉っぱの表面が白い粉のようになる物の正体はうどん粉病菌の菌糸と胞子です。
よく使われている散布剤
予防剤
害虫に対しては速効性と持続性(アブラムシで約1ヶ月)を実現
病原菌の侵入を防いで病気を未然防止します。
スポンサーリンク
治療剤
様々な野菜やハーブ、果樹などでも使えます。
有機JAS規格(オーガニック栽培)で使用可能な食品成分から生まれた殺虫殺菌剤です。
ワイド集中切り替えノズルから噴霧される薬剤がアブラムシ、コナジラミ、ハダニ、うどん粉病をしっかり包み込んで退治する『物理防除剤』で化学合成剤に抵抗性がある害虫や耐性のある菌にも効果的です。
嫌な臭いも無く野菜や果樹の収穫前日まで使え、使用回数の制限もありません。
スポンサーリンク
まとめ
以上、予防剤と治療剤の違い、カビの胞子が病気を発生させるまでの経緯、散布薬剤の選び方についてまとめてみました。
育てている草花や野菜に病害虫が発生しないようにしっかりと予防対策をして美味しい野菜を沢山収穫出来たらと思います。
ここまでご精読ありがとうございました。