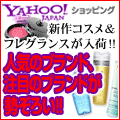2024年2月28日 更新
熱帯魚ファンのみなさん こんにちは
120㎝水槽も余裕で乗せることが出来る自分だけの丈夫な水槽台を作ってみませんか?
追記内容
・組み立て順序①~⑩を図解
・万一への備えに吸水マット
熱帯魚飼育で使っている水槽って、かなりの重量がありますが、今の水槽台で大丈夫かな?チョット強度面で不安になるなと思っている方も多いと思います。
※水槽置台を自分で作りたいと思っているけど難しそう。
※水槽台の高さは低くても良いから、頑丈なものが欲しい。
そんな方に、ホームセンターで購入出来る安いパイン材で簡単に作れる木製水槽台をご紹介したいと思います。
耐震性能も含めて圧倒的な強度と安心感

目次
手作りの丈夫な水槽台
一般的に水槽台は椅子に座った姿勢で見る高さに設計されている様に思います。
市販品には木製の物や鉄製の薄いアングルで組み立て式のもの等、様々な仕様、タイプの違う物が沢山有ると思います。
もちろんメーカー品の水槽台は十分な強度、耐久性を持っているものばかりです。
今私が飼育しているアロワナの水槽は120㎝で、普通の枠有のものです。
120㎝水槽ともなると、水量も240リツトルを越え、水槽本体だけでも30㎏以上はあるため総重量は270㎏以上に達するとても重たい物を水槽台に乗せることになります。
私の場合は、低い位置に座ってゆっくり鑑賞したいと思っていたので、自分に合った水槽台を作れないかと考えていました。
しかし、そんな重たい水槽を部屋に置くとなると、床下の強度も気になります。
やはり水槽台本体をどの様な形や構造にすれば見易くて強度的にも満足を得られるものが出来るか検討し、自分で納得出来る水槽台を作る事にしました。
この時点で素人の私が考えると、おそらく過剰強度の物が出来上がりそうな予感がしていました。
独自の設計コンセプト
①どんなに重たいものを乗せても潰れない強度を持ったものにする。
※材料を重ね合わせて接着するログハウスをイメージした組み立て工法!
➁床との設置部分の面積を出来るだけ広く取り加重が集中しない構造にする。
③座椅子に座って鑑賞するのに丁度良い位の高さで40cm以下程度とし、横幅は水槽の幅よりも10㎝位は余裕を持たせること(横ズレ防止の取り付けに必要)
④可能な限り耐震性を持たせる工夫をすること。
以上4つの設計コンセプトで製作準備に取り掛かることにしました。

水槽台本体材料の手配
初めに全体のイメージ図を作成して、縦・横・高さを決めて設計図面を引きました。
次に本体の構造物となる材木を購入するためにホームセンターに向かいました。
一般的に何処のホームセンターにも置いてあるパイン材で厚みが38㎜、横幅が89㎜、長さ3600㎜の材料を10本購入して図面に従ってカットを依頼しました。(ホームセンターで1000円前後/本)
カット依頼寸法
➀長さ900㎜×12本(天板になる部分) ※幅900㎜の水槽台2セット分の材料
②長さ534㎜(水槽幅45㎝よりも84㎜余裕あり)×48本 ※(水槽台2セット分)
組み立て順序を図解
イメージ画像を追加しました。

※幅900mmの水槽台を2台製作して横並べしたものです。
※90cm水槽単体でも使えるのと、1500cmまでなら外部フィルターも乗せられます。
とにかく強度は抜群なので、圧倒的な安心感があります。

組み立て手順①~⑩
➀足になる部分(材料長さ534×38)を8本横に重ね合わせて木工用のボンドで接着。
※38㎜×8本で304㎜、プラス天板の厚み38㎜で合計342㎜、この寸法が水槽を置く高さになります。(座椅子に座って鑑賞する高さを想定)
※8本重ね合わせた物を1SETとして(足の部分になる)全部で6SET組み立てます。
➁天板になる材料を(長さ900㎜×横幅89㎜)床に横置きに6本並べて(幅を534㎜)ボンドで接着(ズレない様に専用の冶具で固定しておきます)
➂天板の接着が乾燥するまで1日待って、足になるセット品を3個均等間隔で並べ、天板になる板の上に置きボンドで接着します。
➃接着が乾燥したら、一旦反転させて長いコーススレッドで天板と足をになる部分を固定します。(Makitaの充電式インパクトドライバーが活躍)
天板の上から足になる部分を長いコーススレッドなどのデッキ材を固定するネジで締め付け完全に天板を接合させます。
天板の上から長いコーススレッド等で足の部分に固定

ネジ締めにはドリルドライバーかインパクトドライバーがあると簡単に作業が出来ます。
スポンサーリンク
※この組み立てにより、上からの加重に対しては完璧と言える強度が確保出来ました。
⑤もう一度反転させて足になる部分の両サイドになる内側部分を頑丈なL字金具で補強して横方向からの加重にも耐える様にしました。
⑥補強が完了後に上下を180度回転させると、水槽を置く天板が上向きになります。

⑦水槽をセットする前に長さ1200㎜で横幅500㎜、厚さ20㎜の平板を置き完全な平面を確保しました。※建築用の水準器で平行確認
⑧水槽の下面にはゴム板を敷いて振動に対して横滑り防止措置を行いました。
スポンサーリンク
⑨水槽本体が振動で前方にずれて来るのを防ぐために木製のストッパーを製作してボルト付けしました。

⑩水槽の上面から下面までを荷役用のベルトを掛け、水槽台の上板に穴を明けてU字金具で固定しました。
スポンサーリンク
(トラックに荷物を載せて固定用のロープでズレ防止をしているイメージです)

※以上のような材料寸法は、作られる方がご自分の用途に合わせて自由に決めていただくことで、自分だけのオリジナル水槽台が出来上がると思います。
スポンサーリンク
設置後8年目の感想
※圧倒的な強度を持った水槽台を作ったことで、見ていても安心感が有ります。
最初に予想した通りの過剰強度の水槽台になったわけですが、自分の設計コンセプトに沿って作り上げたことで満足しています。
万一への備えに吸水マット
耐震に対する工夫点では、水がなるべくこぼれないように、水位を60%にしています。
又、万一こぼれた場合に備えて、給水マットを水槽台の下に敷詰めています。
スポンサーリンク
お風呂場で使うような、マイクロファイバーの足マットも水分を即効で吸収するので大変役にたちます。
スポンサーリンク
※大きな地震には当然耐えられるようなものではありませんが、自分で出来ることは精一杯やっておくことが熱帯魚管理者にとって大切ではないか思いました。
長々と書きましたが、手作り水槽台がどなたかの目に留まりましたら幸いです。
まとめ
今回ご紹介した丈夫な水槽台は、上部からの加重や、横揺れによる水槽のズレ等にも対応出来るように設計した、安心して使える一生物の水槽台です。
関連記事